時は移ろい、人は老いて、やがていなくなる。これは定められた運命であり、何人たりとも避けられない結末。生と死は排反し、死は消失を意味する。でも本当にそうか?
***
皆川博子 作、日下三蔵 編の『昨日の肉は今日の豆』を読んだ。
やはり凄い。ますます筆運びが自由に、軽やかになっていくように感じられる。先述のような生物学的な死によってのみ生を規定する捉え方に対して、「他にもこんな考え方もあっていいのでは?」と朗らかに微笑むような趣だ。
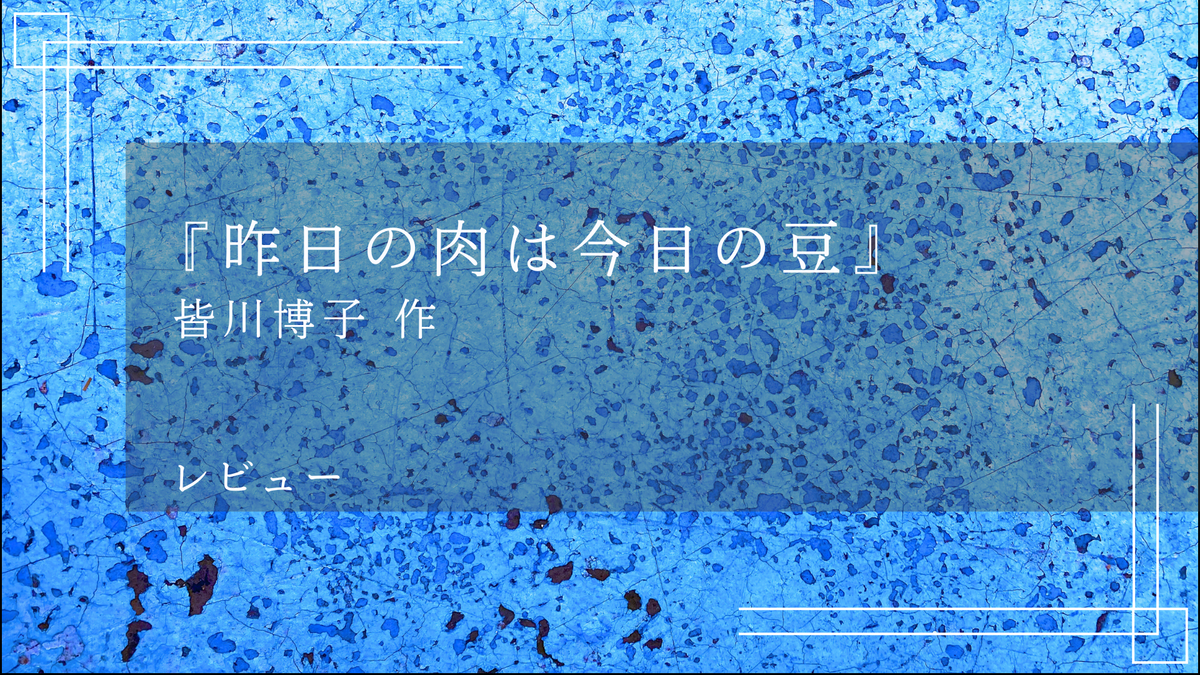
概要
『昨日の肉は今日の豆』は、2010年~2025年にわたる幻想小説・詩歌28篇を集めた短編集である。
最初に書籍情報が出てから、刊行日が近づけば遠のくといった具合で、何かあったのだろうかと心配していたけれど、ようやく手に取ることができた。心待ちにしていました。そして通読後は、満たされた心地です。
収録作のレビュー
中でも印象に残った収録作7篇についての感想を。
「夏を病む」
右の道を行ってはいけない。周囲の年長者たちから、訳も教えられず、そう言い聞かされる少女。しかし、意図せず二又道の選択を間違えたことで、時の流れが歪む夢幻世界に迷い込んでしまう。いや、あるいは未来へ遡行していく、のだろうか。
少女の幼いみちゆきの転換点で、見知らぬ男が漏らす独り言がとりわけ異質である。曰く、
途方もない大きな力が、世界をこう、ぐいっと捻るんですね。(中略) あったものは消え、ないものは創り出されます。でも、消されたようでも、痕跡はどこかに残るのです。
一見、不条理な悪夢に似た幻想小説の態をとる作品だが、一方で、敗戦前後での価値観の劇的な転換と、それによって自家撞着を起こす社会への不信という、作者の原体験が構造的に反映されていそうだ。
「ララバイ」
「一生で一番難儀なところは通り過ぎた」と、軽妙なユーモアでもって生死の境界を越境する〈私〉。衒学的で偏屈そうな語り口と裏腹に、個人の領域を侵犯しない他者への眼差しは案外温かくもある。
今日も〈私〉は若者へのささやかなエールを送るのだろう。その安らかな休息を願って。
「昨日の肉は今日の豆」
「豆化症」なる疾病が流行する社会で、「老化現象は感染する」「老人をすべて隔離せよ」との理不尽な社会の声に困惑しながらも、老女は、環境に適応しつつ、夫と共に慎ましく生きている。
題名は「昨日の敵は今日の友」をもじったものだと分かるが、どうやらこの言葉は、日露戦争末期における両国将軍の会見でのエピソードに由来し、軍歌「水師営の会見」の一節として歌われたのだそうだ。老女が言及するのも同曲であり、作中では「日の御旗」という語が伏せられている。
時代や取り巻く事情が変われば、社会の道理は簡単に手のひらを翻す。戦中は尽忠報国の象徴として称揚されたものが、戦後はその経緯ゆえに使うことが憚られる語となる。昨日の正義は、今日の悪。
地上のことわりの移ろいやすさをアイロニカルに描きながらも、時代に、環境に適応して生きていかざるを得ない明朗な諦念と生のしなやかさを感じた。
「夕の光」
本書の後半パートに収録されている作品群は、2020年代に入ってからのものが多く、とりわけ老人ホーム生活についての記述が散見される。
本作品でも、老人ホームに身を置く無聊を慰めるように、愛好の詩歌を参照しながらこれまでの来し方を振り返る。肉体的な老いの事実とその先にある暗がりを認め、それでも「ふみを読み、ふみを綴る力」が残されていることを感謝する日々があり、それがまるで祈りのようだと吐露する。最も素直な、近年の作者の胸中を表しているのではなかろうか。
「風よ 吹くなら」
通り過ぎていく数々の人の生と死を前にした寂寥と、それを受け入れる潔さとが混ぜになったような心境を詠んだ散文詩。皆川版「外側の生のバラッド (ホフマンスタール)」のような印象を受けた。
人の絶えた夜、「駅は二つに折りたたまれる」という夢想において、大きな伽藍を占拠する不在の様相は、日中、駅を通過していった人々の存在を強く想起させる。少し前まで彼らが確かにそこに居たという証左、「命たちの痕跡」はどこに残るのだろうか。
そこから連想はさらに進み、器としての肉体から区別された「肉体の中にあった不可視のもの」の存在が浮かび上がる。魂ともイマジネーションとも呼べそうなそれは、肉体から漂い出て飛龍のごとく跳躍する一方で、影であるところの肉体は小さく萎んでいく。
ここから先は明言されないが、やがて肉体が滅びるとき、「不可視なるもの」は位相をかえて「命たちの痕跡」となるのではないか。草葉の陰に隠れた先人たちの言葉や物語がいまも私たちに語りかけるように。本作品は、いつか訪れるその瞬間に向けた、謙虚な作者の願い事をも表しているのかもしれない、そう考えたりしたのだった。
「香妃」
文体のリズムと濃縮された時の密度にただただ圧倒された。
戦火で焦土と化した原を幻視し、歳月に蝕まれていく原を幻視し、「死者の無惨が凝って香となった花」に、「過ぎし時の中でのみ、逢っていようね、香妃」と呼びかける。あまりに大きすぎる楔を打ち込まれた時、人は在りし日の体験の中を永遠に揺蕩いつづける。
戦時の記憶を「弊履(へいり)」と捨てたのが西條八十だとして、そんなことが容易に出来るわけもないとして、「戦火を知る身は哀しい」と零すような葛藤が、先述の短編「夕の光」でも言及されていたが、それと同種のものが血の跡と共に滲んでいる。
「Lunar Rainbow」
「まわりの誰しもが何かしらの哀しみの石を秘かに抱き、時とともに老い、いなくなる」という鳥瞰での無常の一文が、この作者から出てきたことが少し新鮮だった。〈異端なる者〉による生死を賭けた血のにじむような語り、というのが作者の物語の原型だと思っていたから。
しかし、誰しもに等しく訪れるところの死、それを見つめるということは、異端/それを含まない社会という相克の構図さえも超越するのかもしれない。
おわりに
冒頭に書いた「生と死は排反し、死は消失」という味気のない固定概念を、本書で綴られる物語たちはやすやすと飛び越える。代わりに描かれるのは、肉体という枷を超えて、個としての輪郭を超えて、自由奔放に駆ける夢想である。
力強く優雅に哀切に軽やかな筆致に、更なる境地へ進化し続ける作者の姿を感じた。